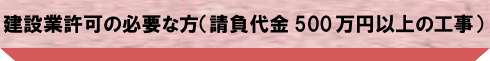|
建設業を営もうとする者は、軽微な建設工事を除いて、建設業の許可が必要です。
1.建設業の許可業種
・建設工事には、下記の28の種類があります。
・許可は営業する業種毎に取得する必要があり、同時に2つ以上の業種の許可を受けられ、現在許可を受けている許可業種に、業種を追加することも可能
です。
・ある業種の許可を受けていても、許可を持ってない他の業種の工事を請負うことは出来ません。(但し、軽微な建設工事を除く。)
| 土木工事業(土木一式) 建築工事業(建築一式) 大工工事業 左官工事業 とび・土工工事業 石工事業
屋根工事業 電気工事業 管工事業 タイル・れんが・ブロック工事業 鋼構造物工事業 鉄筋工事業
舗装工事業 しゅんせつ工事業 板金工事業 ガラス工事業 塗装工事業 防水工事業 内装仕上工事業
機械器具設置工事業 熱絶縁工事業 電気通信工事業 造園工事業 さく井工事業 建具工事業
水道施設工事業 消防施設工事業 清掃施設工事業 |
2.建設業許可は必要でない方(軽微な建設工事)
| 建築一式工事以外の建設工事 |
1件の請負代金が500万円未満の工事(消費税含む) |
| 建築一式工事で右のいづれかに該当する工事 |
(1)1件の請負代金が1,500万円未満の工事(消費税含む)
(2)請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事(主要構造部が木造で、延べ面積の1/2以上を居住の用に供するもの) |
3.許可の種類
●大臣許可と知事許可
| 国土交通大臣許可 |
2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設ける場合 |
| 都道府県知事許可 |
都道府県内にのみ営業所を設ける場合 |
※ここでいう営業所とは、建設業を営むための常設の事務所を有し、看板等の表示のほか、
見積り、契約等の実態的な業務を行っている事務所のことであり、現場作業所や連絡事務所
などは、営業所に含まれません。
※営業所の要件については、許可の審査に際し、立入調査を行うことがあります。
※県知事の許可を受けた業者は、営業活動は県内の営業所で行わなければなりませんが、その営業所における契約に基づいた工事は、
県内以外でも施工可能となります。
※大臣・知事の許可を問わず、営業の区域又は建設工事を施工する区域についての制限等はありません。
●特定建設業許可と一般建設業許可
| 一般建設業許可 |
下請に工事を出す代金の額が下記に満たない場合。下請けとしてだけ営業する場合。 |
| 特定建設業許可 |
発注者から直接請負った建設工事について一件あたりの合計額が3,000万円以上(建築工事業の場合は4,500万円以上)の下請契約を下請人と締結して施工させる場合。 |
両方受けることは可能ですが、同一の業種について、両方の許可は受けられません。
【一般建設業許可と特定建設業許可の違い】
|
【一般建設業】 建設業許可業者(元請業者) →→ 工事の全てを自社で施工
↓
【一般建設業】 一部を下請けに出す →→ 下請け金額の合計3,000万円未満
(建築一式工事は4,500万年未満)
↓
【特定建設業】 下請け金額の合計3,000万円以上
(建築一式工事は4,500万円以上) |
※ここでいう下請金額の合計とは、その1件の工事にかかるすべての一次下請業者に対する
下請金額の合計です。二次以降の下請に対する制限はありません。
※特定建設業許可が必要となるのは、あくまで元請契約により受注した場合に限ります。
※特定建設業者以外が、元請契約により受注した工事を合計3,000万円以上(建築工事の場合は4,500万円以上)
となる下請契約により、
工事を施工させることはできません。
違反した場合には、罰則の適用があります。
また、下請契約の相手方となった下請負人に対しても、指示等の監督処分をすることができるようになっています。
4.許可の有効期限
・許可のあった日から5年目の許可日に対応する日の前日をもって満了となります。
・期間が満了する日の30日前までに、当該許可を受けたときと同様の手続きにより更新しなければなりません。
・手続きをとらなければ、効力を失い、許可業者としての営業をすることができなくなります。
・更新の手続きをとっていれば、期間の満了後であっても許可がおりるまでは、前の許可が有効です。
5.建設業許可の要件
・一般建設業許可
・特定建設業許可
●一般建設業許可の要件
一般建設業許可を取得するためには、次の要件を全てみたしていなければなりません。
|
経営業務の管理責任者(右に
掲げる要件のいずれかを備えている者)を置いていること
「経営業務の管理責任者としての経験」とは、具体的には、役員、個人の事業主、建設業を営業する支店又は営業所等の長(令3条に規定する使用人)の地位にあって、経営業務を総合的に執行した経験を指します。
|
許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有すること。 |
| 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有すること。 |
| 許可を受けようとする建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって経営業務を補佐した経験を有すること。 |
| 専任の技術者を有していること |
国の定めた資格要件に該当する者を1人以上常勤で配置していること。 |
| 請負契約に関して誠実性を有していること。 |
建設業の許可を受けようとする者が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をする恐れがないこと。(過去に許可を取消されて5年を経過しない者、、営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者などには許可できません) |
| 財産的基礎又は金銭的信用を有している(右に掲げる要件のいずれかを備えている)こと |
自己資本の額が500万円以上であること。 |
| 500万円以上の資金を調達する能力(500万円以上の資金について取引金融機関の預金残高証明書等を得られること)を有すること。 |
| 許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること。 |
| 欠格要件に該当しないこと |
許可申請の書類の中で、重要な事項について虚偽の記載をしたり、重要な事実の記載を欠いたとき。 |
| 個人の場合は、申請者本人又は支配人、法人の場合は役員又は政令で定める使用人のすべてが建設業法第8条に規定する欠格要件のいずれにも該当しないこと。 |
※許可申請書及びその添付書類に虚偽の記載をするなど不正の手段により許可を受けた場合、
その許可は取り消しとなります。また、許可を取消されてから5年間は欠格要件に該当するため、許可を受けることはできません。
●特定建設業許可の要件
特定建設業許可を取得するためには、一般建設業の要件のほか、技術力及び財産的基礎に関してより高い要件を満たす必要があります。
|
1級相当の技術力を有していること。 |
指定7業種(土木・建築・電気・管・鋼構造物・舗装・造園)
1級の国家資格者又は国土交通大臣が特に認めた者を常勤で配置していること |
|
指定7業種以外
一般建設業許可の専任技術者の要件及び指導監督的実務経験を有する技術者を常勤で配置すること。 |
|
財産的基礎又は金銭的信用を有している(右に掲げる要件の全てに該当する)こと
(5年ごとの更新時にも要件を満たす必要がありますので、申請前に十分確認してください。要件を満たさないときは、申請を取り下げていただきます。この場合、申請手数料はお返しできません。) |
資本金が2,000万円以上であること。 |
| 許可を受けようとする直前の決算期における流動比率(流動資産/流動負債)が75パーセント以上であること。 |
| |
|
許可を受けようとする直前の決算期における自己資本の総額が
4,000万円以上であること。 |
|
許可を受けようとする直前の決算期において欠損がある場合、
その額が資本金の20パーセント以内であること。 |
6.申請手続きの流れ
●許可申請書類の入手 (許可申請書と添付書類一覧=表 1 )
許可申請に必要な書類は、各都道府県の建設業協会及び各支部等で販売されています。
●許可申請書類の提出先(提出窓口は、各都道府県建設業許可事務担当課)(表 3 ・
表 4)
| 国土交通大臣許可を申請する |
都道府県知事を経由して、各地方整備局長に提出する。
提出部数:正本1部及び営業所のある都道府県の数と同一部数の複本 |
| 都道府県知事許可を申請する |
営業所の所在地を管轄する事務所を経由して、知事に提出する。
提出部数:正本1部及び副本2部 |
●許可申請の手数料/登録免許税の納入
| 国土交通大臣 |
新規許可登録免許税 |
15万円 |
国税局/税務署宛に銀行・郵便局等を通じ納入、納付書を正本に貼付 |
|
許可の更新及び
追加許可 |
5万円 |
収入印紙を正本に貼付 |
| その他上記の組合せにより、加算されます。 |
| 都道府県知事 |
新規許可 |
9万円 |
収入印紙又は現金
※都道府県によって異なります。 |
|
許可の更新及び
追加許可 |
5万円 |
収入印紙又は現金
※都道府県によって異なります。 |
| その他上記の組合せにより、加算されます。 |
●処理に要する期間
| 国土交通大臣許可 |
申請書受付後、おおむね 3ケ月 |
| 都道府県知事許可 |
申請書受付後、おおむね 30日 |
※提出からの期間ではありません。窓口審査が終了し、受付を済ませてからの期間です。
●更新申請の受付期間
| 国土交通大臣許可 |
5年間の有効期間が満了する日の2ケ月前から30日前まで |
| 都道府県知事許可 |
5年間の有効期間が満了する日の3ケ月前から30日前まで |
※決算変更届を提出していない場合は、更新の申請が受付けられませんので、決算が終われば、必ず届出をしてください
7.変更等の届出 (変更等の届出事項と提出書類 = 表 2 )
・建設業の許可を受けた後、申請内容に変更等があれば必要な書類を添付した変更届出書を提出しなければなりません。
※必要な届出をしていない場合には、追加申請・更新申請ができません。
※変更届の提出がない場合、経営事項審査日程や説明会に関する案内はがきがお手元に届かなくなることがあります。
※届出義務違反に関し罰則規定があります。
|
届出事項 |
提出期限 |
| 決算報告書等 |
営業年度終了後、4ケ月以内 |
| 経営業務の管理責任者 |
事実発生から2週間以内 |
| 専任技術者 |
| 国家資格者等・監理技術者 |
| 令第3条の使用人 |
| 商号又は名称 |
事実発生から30日以内 |
| 営業所(名称、所在地、新設、業種) |
| 資本金額(出資総額) |
事実発生から30日以内 |
| 役員 |
| 個人の事業主(又は支配人) |
| 廃業届 |
8.許可の通知と証明願・閲覧
・許可の通知は、「許可通知書」を主たる営業所(本社)へ郵送します。
窓口交付は行っていません。
・「許可通知書」は再交付しません。紛失した場合や、商号変更等で証明が必要な場合は、
「建設業許可証明書」の発行を申し込んでください。
「建設業許可証明願」に記入、申込み。(来庁・インターネット・ファックス)
・手数料 1通につき400円を現金で納入してください。
・インターネット・ファックスによる申込みでも証明書の受取の際には、必ず来庁ください。
・許可申請書及び変更届出書等の閲覧ができます。
詳しくは、各都道府県建設業許可事務担当課にお問合せください。
9.不服申立方法
行政不服審査法の規定による。(異議申立、審査請求、再審査請求)
|